音を楽しむとは何か探求する in 同好会ライヴ
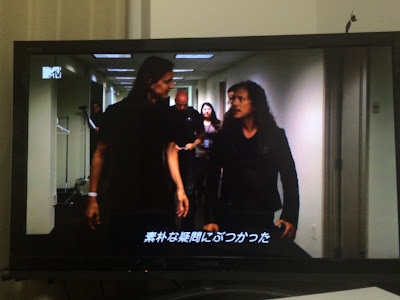
「音楽は音を楽しむことだ!」なんてのは問いが浅いと、メタル人類学者サムダン氏の問いぶりを見て思い知る。 家族を顧みず休日を音楽同好会ライヴイベントに費やす我々が、何を通してどのように音楽を楽しむのかは探求すべき使命感がある。 ■ライヴイベント当日のフロー 駅から徒歩5分を歩いてライブハウス入りするのは出演者も観客も同じ。 会場入りしながらMCネタを探す。観客の共感を誘う時事ネタやポケストップを足で稼ぐ。 フライヤーも手作り。多忙な中で企画から運営までこなす主催者に感謝。 お世話になるライヴハウスのマスターにご挨拶。会場設営に自由度があり、例えば場内禁煙かは主催者次第。 マスターがPAも兼任していて、リハーサルが始まるとタブレットアプリで操作する。 PA卓から出音のバランスをとるだけでなく、タブレットを持って演奏者の立ち位置に移動し、ステージ上のモニター音も調整する。 リハーサル後はアンプつまみ位置を写真を撮る。 本番前の転換では短時間で確実にセッティングしないといけない。撮影しておけば思い出せて安心。 出演順と反対にリハーサルをする「逆リハ」方式。1番目の出演者が転換なくセッティングで出演できて効率的。 逆リハだと、「トリ」出演者は最初のリハーサルから最後の出番まで気が抜けない。合間の昼食で生280円を我慢するプロ根性は持ち合わせていない。プロじゃないし。 スタジオに戻ると、機材を引っ下げた出演者が続々登場する。音へのこだわりと身軽さはトレードオフ。 屋根裏みたいな控室は、JR高架下のため電車の音がゴリゴリ伝わる。準備する出演者のソワソワも伝わる。 リハが終わって顔合わせ。同好会の顔見知りの他、今回は他社ゲストもいる。 観客が入場すると、再入場のためのスタンプを手に押す。 観客の有り難さを知るが故に、他の出演者のときは観客に徹する。 Tシャツは嗜好を伝えるコミュニケーションツール。 コード進行だけが決まった、飛び入り歓迎のセッション。普通のライヴイベントだと出来ない。 時間終了の合図が出てなお没頭する奏者に、「終われない!」とアイコンタクトする奏者。スリリングな進行。 ■脳内マップは人それぞれ 音へのこだわりが凄いギタ...

